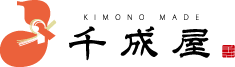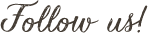成人式で振袖を着た後にクリーニングは必要ない?湿気が気になる梅雨の季節はどうすべき?
2025年06月01日

振袖は日本の伝統的な衣装。
高い技術を持った職人が長い時間をかけて繊細に丁寧に作りあげていくものです。
そんな振袖の美しさを長く維持するためには、適切なクリーニングとメンテナンスが必要です。
現代の生活環境では、着物を着用する機会は限られています。
特に振袖は未婚女性のみ着られるもののため、成人式や結婚式のお呼ばれの際に着用するなど、より限定的となります。
しかしながら、振袖は大切にケアをしていけば、何十年も綺麗に着ることができるもの。
だからこそお家の振袖を大切に扱い、次回も美しい状態で着られるようお手入れすることが重要です。
着物に馴染みのある方が少なくなってきているからこそ、お持ちの振袖をどうしたらいいか分からない方もいることでしょう。
そこで今回はメンテナンスの仕方が分からないという方に、様々な方法や保管のしかたをご紹介します。
- <目次>
- ・なぜ振袖のクリーニングが必要なのか
- └振袖の生地の作り方
- └汚れや傷みへの変化
- ・梅雨に気を付けること
- └たまった湿気による影響
- └虫害対策
- ・クリーニングの重要性
- └京洗いと丸洗い
- └しみ抜きと色補正
- ・家庭でできるメンテナンス方法
- └着用後の基本ケア
- └正しい畳み方と保管方法
- └定期的な虫干し
- ・季節に応じたメンテナンススケジュール
- └春(3月~5月)
- └夏(6月~8月)
- └秋(9月~11月)
- └冬(12月~2月)
- ・振袖を家の着物として長く愛用するために
- └成人式後のクリーニングの重要性
- └振袖特有のメンテナンスポイント
- └家族で受け継ぐための保管方法
- └サイズ直しとリメイクの可能性
- └思い出を保つための記録保管
- ・まとめ
。
なぜ振袖のクリーニングが必要なのか
正しくメンテナンスを行うために、まず振袖がどんな素材で作られているのかをお伝えします。
1.振袖の生地の作り方

振袖は基本的に絹を100%使用した「正絹(しょうけん)」と呼ばれる素材で作られており、一般的な洋服とは構造と素材が異なります。
振袖の作り方として、まず「お蚕様」と呼ばれている蚕(かいこ)に桑の葉を食べてもらい、作られた繭をほどき糸を寄り合わせます。
その糸を正絹の布として織り、染料を用いて生地を染め、手書きで柄を描いていきます。
熟練職人の技術と年単位で長い時間をかけた工程を経て、振袖が出来上がっていくのです。
2.汚れや傷みへの変化

絹を中心とした天然繊維は美しい光沢と風合いを持つ一方で、湿気や汚れに対して非常にデリケートです。着用後にそのまま放置してしまうと、目に見えない皮脂や汗、食べ物の匂いなどが繊維に染み込み、時間の経過とともにシミやカビの原因となってしまいます。
特に、振袖の袖口や襟元、裾などは外気に触れやすく、また体に密着する部分でもあるため、汚れが付きやすい箇所です。これらの部分に蓄積された汚れは、放置すると繊維を劣化させ、最悪の場合は修復不可能な状態になってしまうこともあります。
また、振袖に使用される染料や金糸、銀糸などの装飾は、汚れや酸化によって色あせや変色を起こしやすいため、定期的なメンテナンスを行うのがおすすめです。
梅雨に気を付けること
日本の梅雨時期は、着物にとって最も過酷な環境条件が揃う時期です。高い湿度と気温の変化は、着物の繊維にさまざまな悪影響を与える可能性があります。
1.たまった湿気による影響

梅雨時期の高湿度は、着物の最大の敵といえます。絹などの天然繊維は湿気を吸収しやすく、湿度が60%を超える環境では繊維の内部に水分が蓄積され、カビの発生リスクが著しく高まります。カビは一度発生すると完全に除去することが困難で、着物の美しさを大きく損なう原因となります。
さらに、湿気は染料の化学反応を促進させ、色移りや色あせの原因にもなります。特に、濃い色の着物と薄い色の着物を同じ場所に保管している場合、湿気によって染料が移動し、回復不可能な損傷を与えることがあります。
2.虫害対策

梅雨の時期は虫の活動も活発になります。特に衣類害虫として知られるヒメマルカツオブシムシやイガなどは、絹や毛などの動物性繊維を好んで食害します。これらの虫は湿度の高い環境を好むため、梅雨時期の着物保管には特別な注意が必要です。
虫害を防ぐためには、着物を清潔な状態に保つことが最も重要です。汚れた着物は虫を引き寄せる原因となるため、着用後は必ず適切なクリーニングを行い、完全に乾燥させてから保管する必要があります。
クリーニングの重要性
着物のクリーニングは、一般的な洋服のクリーニングとは全く異なる専門的な技術と知識を必要とします。着物専門店のクリーニングは、着物の構造、素材、染色方法、装飾技法などに精通しており、それぞれの着物に最適なクリーニング方法を選択することができます。
1.京洗いと丸洗い

着物のクリーニング方法には主に「京洗い」と「丸洗い」があります。京洗いは着物を解いて反物の状態に戻してから洗浄する伝統的な方法で、縫い目の部分もしっかりと洗えるため、最も徹底的なクリーニングが可能です。しかし、再度絵柄を合わせて縫い直す必要があり時間とコストがかかるため、現在では特別な場合にのみ行われます。
一方、丸洗いは着物の形を保ったまま専用の溶剤で洗浄する方法で、現在の主流となっています。この方法では、着物の形を崩すことなく、効果的に汚れを除去することができます。ただし、水溶性の汚れには対応できないため、汗染みなどがある場合は別途処理が必要になります。
2.しみ抜きと色補正

着物についたシミは、その種類と付着してからの時間によって処理方法が異なります。専門業者では、シミの成分を分析し、汚れに適した薬剤と技術を用いてシミを除去します。また、長年の使用により色あせた部分については、熟練の職人によって色補正を行ったり、上から新しく柄を描いたりすることで、元の美しさを取り戻すことが可能です。
家庭でできるメンテナンス方法
専門クリーニングに出す前に、家庭でできる基本的なメンテナンス方法を実践することで、着物の状態を良好に保つことができます。
1.着用後の基本ケア

着物を脱いだ後は、まず全体をやさしくブラッシングして、表面についたホコリや小さなゴミを除去します。この際、毛足の柔らかい着物専用ブラシを使用し、必ず繊維の方向に沿ってブラッシングすることが重要です。
次に、着物を着物ハンガーにかけて、風通しの良い場所で十分に乾燥させます。この際、着物が直射日光に当たってしまうと染料が変色してしまう「色やけ」を起こすため、室内の陰干しで行います。湿気が完全に飛ぶまで、少なくとも一晩は干しておきましょう。
2.正しい畳み方と保管方法

振袖の保管において最も重要なのは、正しい畳み方です。着物には「本畳み(ほんだたみ)」という伝統的な畳み方があり、この方法に従って縫い目に沿って畳むことで、不要なシワを防ぎ、形を美しく保つことができます。
畳んだ着物は、たとう紙に包んで保管します。たとう紙は湿気を適度に調節でき、また虫害からも守る役割を果たします。
ただし、たとう紙は和紙で作られており長期的に保管しておくと劣化してしまうため、定期的に交換する必要があります。特に梅雨時期の前後には新しいものに交換することが推奨されます。
合わせて除湿剤や防虫剤を一緒に入れておくのもおすすめです。除湿・防虫効果のあるたとう紙もありますが、専用の物を用意して別添で置いておくとより効果的です。
除湿剤を選ぶ際、液体タイプやタブレットタイプなど様々なものがあり迷う方もいるでしょう。
液体タイプの除湿剤は、劣化によりパッケージが破れてしまい、中身が着物に付着してそのまま汚れや傷みにつながってしまう場合があります。
着物に使用する場合は、着物専用で水気がないものを選ぶのがおすすめです。
3.定期的な虫干し

着物の長期保管において「虫干し」は欠かせないお手入れです。年に2~3回、乾燥した晴天の日に、着物を風通しの良い場所で陰干しします。これにより、保管中に蓄積された湿気を除去し、虫害を防ぐことができます。
虫干しの際には、着物の状態を詳しく確認し、シミや虫食い、色あせなどの異常がないかを確認します。問題を発見した場合は、早めに専門店に相談することで、被害の拡大を防ぐことができます。
季節に応じたメンテナンススケジュール

着物のメンテナンスは、季節に応じた内容に従って行うことが効果的です。
1.春(3月~5月)
春は虫干しの最適な季節です。冬の間に蓄積された湿気をすっきりさせましょう。この時期に年1回の専門クリーニングを依頼することもおすすめです。
2.夏(6月~8月)
梅雨時期から夏にかけては、特に湿度管理に注意が必要です。エアコンや除湿機を活用して、保管場所の湿度を50%以下に保つようにしましょう。また、防虫剤の期限が切れていないかも確認し、必要に応じて交換します。
3.秋(9月~11月)
秋は夏の高温多湿から解放される時期で、着物の状態をチェックする絶好の機会です。夏の間に発生した問題がないかを確認し、必要に応じて専門業者に相談します。
4.冬(12月~2月)
冬は比較的湿度が低く、着物の保管には適した季節です。しかし、暖房による乾燥しすぎにも注意が必要で、適度な湿度を保ちましょう。
振袖を家の着物として長く愛用するために
成人式で着用した振袖を、その後も家族の大切な着物として受け継いでいくケースが増えています。一生に一度の成人式の思い出が詰まった振袖を、娘や孫の世代まで美しい状態で残すためには、特別なお手入れが必要です。
1.成人式後のクリーニングの重要性

成人式当日は、写真撮影や式典参加、友人との食事など、一日中振袖を着用することが多く、普段の着用よりも汚れが付きやすい環境にあります。また、振袖の袖は長く、慣れない着物での活動により、気づかないうちに袖や裾に汚れが付着していることも珍しくありません。
成人式後は、必ず専門店によるクリーニングを依頼することをおすすめします。なかなか着る機会がないからこそ、目に見える汚れだけでなく、皮脂や汗、香水や化粧品の匂いなどもしっかりと除去し、長期保管に適した状態にしてもらうことが重要です。
2.振袖特有のメンテナンスポイント

振袖は一般的な着物よりも袖が長く、華やかな装飾が施されていることが多いため、特別なメンテナンスが必要です。
長い袖は地面に触れやすく、また動作の際に様々な場所に接触したり踏んでしまう可能性があります。そのため、袖の裾部分は特に注意深くチェックし、小さな汚れも見逃さないようにする必要があります。また、金糸や銀糸、刺繍などの装飾部分は、時間の経過とともに変色や劣化が進みやすいため、定期的に専門家による点検を受けることをおすすめしています。
3.家族で受け継ぐための保管方法

振袖を次の世代に受け継ぐためには、20年、30年という長期間の保管を前提としたお手入れが必要です。
可能なら振袖専用の桐箪笥や防湿庫での保管を検討しましょう。桐は調湿効果があり、また防虫効果も期待できるため、着物の長期保管に最適です。一般的な洋服タンスでの保管は、湿気や虫害のリスクが高いため避けた方がよいでしょう。
また、10年に一度程度は専門業者による総点検を受け、必要に応じて色補正や修繕を依頼することも重要です。小さな問題を早期に発見し、適切に対処することで、振袖の価値と美しさを長期間保つことができます。
4.サイズ直しとリメイクの可能性

振袖を受け継ぐ際に考慮すべきは、体型の違いによるサイズの問題です。現代の女性は過去の世代と比べて体型が変化しており、母親や祖母の振袖がそのまま着られない場合があります。
しかし、着物は洋服と異なり、ある程度のサイズ調整が可能です。袖丈や身丈の調整、身幅の変更など、専門の職人による仕立て直しにより、現代の体型に合わせることができます。ただし、この作業には高度な技術が必要で、また元の着物にある程度の余裕が必要なため、着用する本人と一緒に事前に専門家と相談することが重要です。
また、どうしてもサイズ直しが困難な場合は、振袖を訪問着にリメイクするという選択肢もあります。袖を短くして訪問着として仕立て直すことで、より多くの機会に着用できる着物として生まれ変わらせることができます。
5.思い出を保つための記録保管

振袖を家族の宝物として受け継ぐ際には、その着物にまつわる思い出や記録も一緒に保管することをおすすめします。
成人式当日の写真はもちろん、振袖の購入時の資料(産地、作家、技法などの情報)、これまでのクリーニング履歴、修繕記録などを整理して保管しておくことで、次の世代に引き継ぐ際により価値のある情報として活用できます。
また、着物に関する家族の思い出やエピソードを文書として残しておくことで、単なる衣服ではなく、家族の大切な歴史の一部として残していけるでしょう。
最後に

着物は単なる衣服ではなく、日本の美意識と職人技術が結集した芸術品です。特に成人式の振袖は、人生の重要な節目を飾る特別な意味を持つ着物として、適切なクリーニングとメンテナンスによって、その美しさと思い出を何世代にもわたって受け継いでいくことができます。
梅雨時期のような過酷な環境下では、より一層の注意と配慮が必要となりますが、専門店による定期的なクリーニングと、日常的な家庭でのメンテナンスを組み合わせることで、着物は長期間にわたってその価値と美しさを保ち続けることができるでしょう。
着物専門店 千成屋(せんなりや)では、
クリーニング・加工・サイズ直しなど、上記すべてのメンテナンスを行っているほか、たとう紙・メンテナンスキットの販売も行っています。
郵送でのメンテナンスも受け付けているほか、着物のメンテナンスに精通した「きものアフターケア診断士」の無料チェックも受けられるので、着物のことがよく分からないという方も、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
【千成屋ひたちなか本店】 |
|---|
| 〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡3912-1 ☎029-272-6422 営業時間:10:00~19:00 定休日:火曜水曜 |
【千成屋神栖店】 |
| 〒314-0116 茨城県 神栖市 奥野谷5558-4 ☎0299-94-8080 営業時間:10:00~19:00 定休日:火曜水曜 |
大切な振袖を次の世代に美しい状態で残すためにも、正しいクリーニングとメンテナンスの知識を身につけ、実践していくことが重要です。一枚の振袖が家族の絆を深め、日本の美しい伝統を未来へと繋いでいく架け橋となることを願っています。